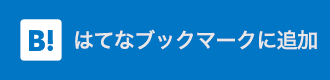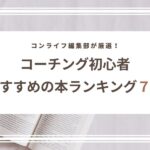目次
1.人脈とは?

辞書を見ると、人脈とは「人や社会との”つながり”」と記されています。一歩踏み込めば「意志の疎通が図られ、アドバイスを求めたり提案できる関係」だと言えます。「自身の価値が相手から認められること」を前提にすれば、相手や集団から頼られる関係にあるということになります。
趣味のサークル、地域活動、営業活動、異業種交流会、研修会や勉強会など、さまざまな場面で人脈を広げるチャンスはあります。効率よく人脈を広げる方法について、具体的に紹介しましょう。
2.人脈は必要?

ビジネスマンにとって人脈は、大きく3つの場面で役立ちます。
「専門的なアドバイスが得られる」「B to C(対個人営業)でいち早く情報が得られる」「B to B(対企業営業)やコラボレーション事業のチャンスが得られる」などが挙げられます。多様化するビジネス環境のなかで人脈によってもたらされる刺激や影響は、見えない大きな価値だといっても良いでしょう。
・人脈を広げるメリットとは?
問題の解決策を考える場合、多方面の専門家の意見や見解が必要です。
ニュース番組でも、高齢者の運転技術を考えるときに「運転技術の専門家」と「脳科学の専門家」に意見を聞くことで、現状把握や解決の道筋を探ります。
企業の販促活動でも、社内チームのアプローチと広告代理店のアプローチが違うといったことはよくあります。異なる立場の意見を集約することで取るべき行動が見えてくるものです。視点を変えた専門性の高いアドバイスは、意志決定の強い支えとなります。
個趣味のサークルや、地域活動を通じた個人の人脈も役立ちます。生活場面に近いため、住宅を建てたいと考えている人の情報を他社より早く知ることもできます。日頃から営業活動を前面に押し出さず、しかし不動産や建築に関連した専門知識を持つアドバイザーとして接していればB to C営業もスムーズに進みます。
最近は、他社と共同プロジェクトも増えています。異業種交流会や研修会などを通じて人脈を広がれば、B to B営業や事業活動のアイデアや商談機会も生まれやすくなります。
・一つの出会いが人生を変える!?
「一つの出会いが人生を変えた」という話は、世の中に溢れています。しかし、その基本にあるのは自分自身の「価値」に相手が共感していることを忘れてはいけません。
異業種交流会などで同じ空間に集ったとします。多くの人たちの中で、存在感が薄いと会話のきっかけは生まれません。集まりに参加したら「第一印象」「会話の内容」「印象に残る質問」を意識して行動することが大切です。
目立ち過ぎない行動をわきまえると、「第一印象」は良くなります。出席者の情報をあらかじめ調べ、控え目でありながら核心と展開につながる挨拶や質問を考えておけば、コミュニケーションに困ることはありません。
話をするきっかけができれば、相手との距離感を意識しながら「前向きな印象」を与えます。ちょっとしたアイデアを投げかけて反応を見ることもできます。
交流が継続する工夫を忘れないようにしましょう。例えば、「質問」によって相手に話をしてもらう工夫です。論点を整理し「今後も、この点についてアドバイスをいただきたい」と、意思を明確に伝えればさらに喜んで応じてくれるようになります。
3.ちょっと待って、その人脈作り間違っています
「自分自身の立ち位置」の問題と関連しますが、勢いに任せて名刺交換のために歩き回るだけでは軽く見られます。簡単なので名刺を工夫しましょう。名刺は、自分をアピールする重要なコミュニケーションツールです。名刺の裏面にオンリーワンの価値を掲載します。自ら積極的に提案し、相手の話をしっかりと聞く姿勢を貫けば「信頼」を獲得することができます。

・異業種交流会での名刺配り
弁護士など社会的評価が高い肩書は少し違いますが、普通は営業部や企画部の名刺です。スローガンと社名、氏名、住所等だけでは、企業名だけでは「本来価値」が見えてきません。
異業種交流会などで求められる情報とは、PRではなく「相手が気づかない価値」です。例えば、建築士の肩書で参加した人が、飲食店チェーンの役職者とコミュニケーションを図ることを想定してみます。一級建築士の肩書を持つ人は多くいますが、それだけでは「ご縁があれば」で終わってしまいます。
そこで、名刺の裏面に「建物の構造だけで売場面積を広げる10の設計テクニック」というキャッチフレーズとミニ解説を掲載します。売場が広がれば、もう一つテーブルが置けるかもしれません。「どうするのか?」知りたくなります。直感的にイメージと重なる工夫をすれば、会話は広がるものです。
・他力本願はダメ!
人脈を作り広げていくときに「個の価値」が大きく影響してきます。商品価値も明確でない、営業マンとしての存在価値もあまり感じない、という人が名刺を差し出し「よろしくお願いします」と言っても、どういう可能性があるのか見えてきません。
「第一印象」「会話の内容」「印象に残る質問」を意識した、交流会などでの立ち振る舞いを紹介しました。簡単に言えば黙っていても「控え目だが、デキる人物」という印象を打ち出すことだとも言えます。
「自分の業務を論理的に整理する」「課題対応策を具体的に立案する」「お客様との将来イメージを明確にする」の三つに注目して、自社商品や自身の価値を整理しておきましょう。「お客様の利益にどう役立つのか?」という直近の利益とともに、将来に向けた共通イメージの共有にも役立ちます。
自分自身に自信が持てれば、せっかく交流会に出向いたのに、知人に紹介してもらって名刺交換をするだけの他力本願で終わることはなくなります。
4.人脈を作り広げる5つの方法

最後は、具体的に5項目を確認します。短い時間の交流会で効率よく人脈を作り広げるために、自信に裏付けられた対応に心がけ、安心感と信頼感を抱いてもらうようにしましょう。考え方に共感が得られれば、人脈作りは成功したと言えるでしょう。
・目的意識を持つ
「お客様との将来イメージ」を具体的な言葉にしておけば、お客様との目標を共有することができます。短時間でお互いの共通点が明確になります。
建築士が「くつろぎ感のある生活環境」と「外気温の変化とホームパーティに強い空間設計」を比べて考えてみましょう。「くつろぎ」という表現だとイメージが曖昧です。「〇〇に強い空間設計」と表現すると「光熱費が減らせる?」「結婚した子どもが帰省してもゆったりできる?」など、生活シーンと重なりやすくなります。建築設計上の工夫で実現できるので、根拠が明確である点が重要です。
参加者の多くは、お互いの可能性が広がることを期待しています。相互の目的にいち早く沿った会話として展開することが重要です。
・新しい環境に飛び込む
人脈を広げるためには、まず面識のない人との最初の出会いを求める必要があります。ビジネスマンであれば異業種交流会などもありますが、趣味や地域のサークル活動でも人脈を広げることはできます。自分の価値を明確にし、集まる人たちの情報を調べれば新しい環境に飛び込む不安はなくなります。
最初から「売り込みのスタンス」を前面に出さないようにしておきましょう。控え目な立ち位置を維持しながら、存在感には意識を集中させます。名刺の裏面に関心を持ってもらえる情報を入れておくと、人脈づくりに大きく役立ちます。
・助けてではなく、与える精神
社外や地域コミュニティへの参加とともに社内でも大切にしたい人脈があります。同期や社内のサークル、また学生時代の仲間や親族なども日頃から親しく交流を続けておくことも重要です。対外的に「アピールし共通認識を持つ」人脈と、同僚などに「アドバイスやサポートを受ける」人脈があります。
新しいアイデアが浮かばないときに、助けを求めたい場合もあるでしょう。しかし、基本は人脈に求めるのは助けではありません。まず自身で課題を明確にして、具体的な「意見」を求めることが基本です。日頃から、専門分野の知識や意見を積極的に発信していると、いざという時に必要な情報を受けることができます。
・自分の強みを理解する
様々な交流のなかで「自分の立ち位置」をわきまえ、「相手との距離」を計り、「相互コミュニケーション」ができる関係を構築するためには、自分自身の強みが明確であることが前提となります。
オンリーワンの価値を明確にして、名刺などを使ってアピールをするようにしておきましょう。「頑張ります」という主張ではなく、「五つの約束」のような論理的整理を習慣にすると良いでしょう。
論点を明確に打ち出す戦略は、共通理解が得やすいため短い時間で強い印象を残すことができます。
・自分の価値を高める
自分自身の価値は、業務全般に関して論理的に整理しておくことから始めると良いでしょう。
人間の価値は「見た目」に左右されると言われています。しかし、会話をすることで別の側面も見えてきます。見た目も大事ですが、自分自身の仕事に対する情熱や知識、技能など、常に検証を行うことを忘れないようにしましょう。考える作業を繰り返し行うことが、自分の価値を高めることにつながります。人脈は、そうした日々の努力が評価された結果だとも言えます。
5.まとめ
人脈を広げるために人が多く集まっている場所に身を置くことが重要ですが、目立ち過ぎる行動をしたために嫌な印象を与えることもあります。
一方で、控え目を意識して多くの参加者と名刺交換ができなかったということでは参加する意味がありません。統計上の傾向を見れば、20%の人とは「良い印象」、40%~60%の人とは「普通の印象」で情報交換をすることができます。
特に、苦手な人を20%程度だと知っておくと不安もなくなります。10人と名刺交換をすれば、6人から8人と良い交流が続けられる可能性が高いのです。自信を持って人脈を広げるようにしてみましょう。