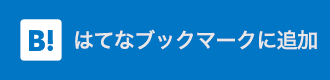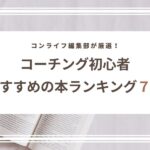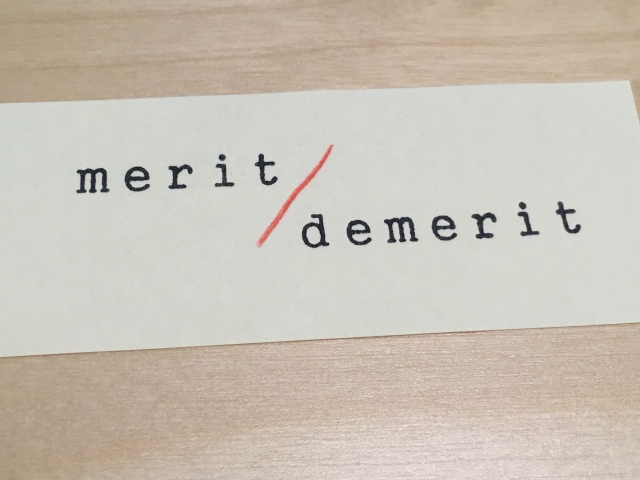
目次
ワークライフ バランスとはどのようなものなの?

ワークライフバランスという言葉を一度は耳にされていると思います。ワークライフバランスという言葉の意味は、「仕事と生活の調和」ということです。ですが、様々な解釈がされています。
具体的には、「国民一人一人がやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活においても、子育て期、中年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる」ということを指しています。
もっと簡単に言うと、仕事と生活(プライベート)のバランスをとることによって双方のプラスになるよう相乗効果を出すことを意味しています。
仕事の効率をアップさせて、パフォーマンスが上がるようにして、生活をより豊かにし、仕事にやりがい・生きがいを持てるようにし、(仕事以外の)生活の時間を有効に活用することで、仕事に対しより意欲的になる、そして短時間でパフォーマンスを上げられる方向へと向かっていくことができるような取り組みをすることなのです。
まずはこのようなワークライフバランスの意味をよく理解をすることが大切です。
ワークライフバランスには以下の二つの概念が含まれています。
・ファミリーフレンドリー
・男女均等推進度
この二つは、ワークライフバランスと似ている概念とされていることもあります。しかし、正確には、ワークライフバランスを構成する二つの重要な要素として考えられています。
「ファミリーフレンドリー」とは、日本語で「両立支援」のことです。
働きながらも育児や介護をしていくための制度・環境を整えることを意味しています。
「働き方改革」
で見直しがされることが多いのは、このファミリーフレンドリーの取り組みです。
「男女均等推進度」とは、男女の性別に関係なく、能力を発揮するための均等な機会が与えられており、性別に関係がなく、評価や待遇の差別を受けないことを意味します。
1985年に制定された「男女雇用機会均等法」が日本での男女均等推進度を明確にすることがはじまりとされています。
「募集」「採用」「配置」「昇進」の全てにおいて、性別を理由にして差別することを禁止しています。
真のワークライフバランスに取り組むには、これらの「男女均等」の考え方がなくてはならないものです。
ワークライフバランスの始まりは・・

ヨーロッパでは、1980年代から女性の社会進出が目覚ましくなり、それに伴ない、ワーク・ライフ・バランスの考え方が広がってきました。
この同じ時代に高度経済成長期の真っただ中にあった日本の社会では、あまりに仕事の方に大きくウェイトが置かれていたため、仕事中毒(ワーカーホリック)になり、過労死や自殺、うつ病などの精神疾患にかかる人々が急増、悲惨な事件が大変多く引き起こされてきました。
また、これまで仕事をしながらも家庭で育児や介護をしなければならない人、特に女性がそのことを理由に休職を余儀なくされ、その結果、解雇されるなどというようなことも数多くありました。
このようなことを踏まえて、女性の「結婚・出産・育児」を支援と男女の雇用機会を均等にすることを考え、政府が少子化対策として、
「育児休業制度の整備」「保育所の拡充」を進めたことに始まります。
しかしその後も、全く少子化の動きが止まらなかったため、2003年に「少子化対策基本法」「次世代育成支援対策推進法」を成立しました。この法律によって、政府が企業に対して「出産・育児と仕事の両立」を支援するための取り組みを義務付けたため、これがきっかけとなって、ワーク・ライフ・バランスの考え方が着目され始めました。しかし、ワーク・ライフ・バランスは女性ためだけのものではなく、男性にも大きく関わってきています。
少子化と同じくらいに深刻な問題があります。
高齢化の問題です。あと数年すると、団塊世代の介護への対策が必要になってきます。
そのため、男性社員であっても「親の介護が必要になったら安心して休みをとれる企業」、「休職した後で復職をしたとしても昇進のチャンスが与えられる企業」といえる職場でないと、優秀な人材が定着することがなくなります。
そういうことで、ワーク・ライフ・バランスの概念は、
①少子化問題に対しての「出産・育児支援」
②高齢化に対しての働き方の改革
以上の2つの理由により、大きな注目を浴びています。
なぜ今、ワークライフバランスが必要なのか?

日本では1980年代まで高度経済成長期にあったため、人々は労働に集中して「企業戦士」として、日本経済を盛り上げていくことが最も重要だと考えられてきました。
仕事は本来、対価であるお金を得ることであり、自分の生活を豊かにするための糧なのですが、あまりに仕事の比重が高くなりすぎたために健康を害す、あるいは仕事のために家庭生活を犠牲にすることを余儀なくされた人々が増え続けました。
しかし、1990年代以降になると、バブル経済が崩壊した直後に経済が停滞し、大企業中心で行ったリストラの影響により、共働き家庭が増えていったこと、そして女性の社会進出が著しくなってきたことなどが理由です。
社会を取り巻く環境が大きく変化して仕事以外のことへの価値を見出していこうという動きが出始めてきました。
それまでの仕事が全てという考え方から、男性は仕事以外の生活に価値を見出していき、女性は結婚や出産後も社会で活躍し続ける人が増えていきました。
雇用している企業側の方で仕事と生活の調和(バランス)を保ちながら仕事をしていくことを考え、ワークライフバランスの考えを取り入れて、推進していく必要性を強く感じるようになってきたからです。
このような社会的背景があって、政府や企業側のリーダーの立場の人達が中心となって仕事と生活のバランスをうまくとっていくことの必要性、つまり、ワークライフバランスの考え方を取り入れることの必要性を強く感じられるようになってきたのです。
「育メン」やワーキングマザーが多くなったのも、こういった取り組みのひとつの現れです。
ワークライフバランスによくある誤解とは?

ワークライフバランスの意味は、様々な解釈がされていることから 誤解をされている方も結構多いようです。
ワークライフバランスを「仕事」と「生活」の重視することをどちらにするとかという問題だと捉えられていることもあるようです。本来のワークライフバランスの意味は、生活と仕事のどちらか一方を犠牲にするというようなものではありません。
そのほかにも、ワークライフバランスとは、仕事とプライベートをきっちりと分ける考え方であるとか、あるいは仕事と生活の時間配分を半々にするようにしていくことが大事だとかいう意味でとらえている方もいるようです。
ワークライフバランスは、仕事と生活のバランスをとるために適している時間比率のことを言っているわけではないのです。
時間の比率も確かにワークライフバランスの一つの要素ではありますが、このことはワークライフバランスの意味の中の一つにすぎません。
そう考えると、ワークライフバランスは仕事の時間を大幅に削って、労働者達の生活の時間を多くとるようにすることであるように解釈されてしまいます。
もしそういうことであれば、仕事に悪影響を及ぼすのではないかというような感じを受けて、企業の経営者の方も導入することから尻込みすることでしょう。
本当のワークライフバランスの意味は、「仕事で成果を上げるために必要な自分の成長やスキルを仕事以外の場(生活)の中から見つけて、仕事の効率を上げるようにメリットにしていく」 という意味なのです。
ワークライフバランスに取り組むことへのメリット・デメリット

ワークライフバランスに取り組みでのメリット
①女性の社員が会社に定着するようになる
「出産・育児」している女性社員に対して、定着しやすいように
・フレキシブルなさまざまな勤務の形態を提案
・出産後に育児支援をできるよう整備する
以上の「育児支援をすること」で、女性社員が出産後も仕事がしやすくなり、育児をしながら仕事を続けられるようになります。その結果として、長く会社に女性社員が定着します。
実際に、初めの子(第一子)を出産する時に退職する女性社員が6割以上を占めていました。
そのため、今後ワークライフバランスの定着・強化に取り組んでいくことで、女性人材が定着し、女性リーダーの育成も実現できます。
②働きすぎによるリスクを回避できる
働くことに重点を置きすぎたことにより、これまで引き起こされていた健康への害、過労死または自殺、あるいはうつ病などの精神疾患になるリスクを避けることができます。
③スキルアップすることができる
ワークライフバランスの取組みを始めたことによって、社内のコミュニケーションが円滑になり、自己啓発や習い事などに自分を磨くことに対して時間を使うことができ、それがスキルアップにつながっていきます。そして、結果的にキャリアを形成していくことができます。
④生産力のアップ
効率よく仕事をこなすにはどうしたらよいのか?会社全体でワークライフバランスに積極的に取り組むことで、一人一人の従業員の労働の「質」が上がって、良い影響がでてきます。
自分のスキルアップ→会社の生産力をアップにつながるというように会社に対しての貢献する気持ちを持つようになります。
⑤優秀な人材の確保
終身雇用制度が崩壊している現在では、優秀な人材を長い期間にわたって確保することが難しくなってきています。求職中の方や新卒の学生に対して、会社として「ワークライフバランス」に取り組んでいるということは、
・社員を大切にする企業
・働く仕組みがフレキシブルな先進企業
というイメージでとらえられて、募集をする上で大きなアピールポイントになります。その結果、優秀な人材が集まることも期待できます。
さらに、優秀な人材を長く定着させることや人材育成や研修コストを有効活用できることにつながります。
⑥社員のモチベーションの向上
ワークライフバランスに取り組むことは、職場全体のモチベーションアップにもつながっていきます。
そして、ワークライフバランスが取れていることは、仕事への意欲を高めていきます。
社員のモチベーションの向上は、「人材育成」「社内のコミュニケーションの向上」「労働生産性の向上」につながります。
⑦企業のイメージアップができる
企業として、「ワークライフバランス」に取り組んでいるということは、「優良企業であること」が大きなアピールポイントになり、優秀な人材を確保することにもつながります。
ワークライフバランスに取り組むことへのデメリット
ワークライフバランスの取り組みを始めても、社内にもともと長時間労働をしてきた風土が定着してると、実際は「絵に描いた餅」になってしまって、利用されないままになってしまいます。実際に、制度だけを取り入れていても、社員が利用できていないという会社が多いようです。
ワークライフバランスの考え方が浸透していくまでには結構な時間がかかります。そのため、実際に結果が出るまでには企業内のリーダーが根気強く、ワークライフバランスに取り組むことに対しての推進力と持続力が重要です。
理想的なワークライフバランスとは?

企業の管理職の行動は重要で、それがどうあるかが効果に大きく影響します。まずは、管理職に理解、推進してもらい、社内に徐々に浸透させていくことが本当にワークライフバランスを社内に根付かせていくために必要になります。
そのためには、重点的に管理職にワークライフバランスの研修をし、社内のリーダーとして率先して促進してもらえるようにしていくことです。
ワークライフバランスの取り組みが成功している 企業
①サイボウズ
「100人いたら、100通りの働き方」という考えを取り入れ、組織内の意識改革、評価制度を見直しする。
背景:2005年以降離職率28%と過去最高を記録。
ワークライフバランスを意識して制度を設置し、社内のコミュニケーションを活性化する施策を行った結果、社員のモチベーションが向上し、生産性もアップした。そして離職率28%→4%という結果。
②レオパレス21
ワークライフバランスを意識して働き甲斐のある職場環境づくりをする。
背景:リーマンショックを契機として最悪の離職率を記録ししていた。
優秀な社員の流出を防ぐために、2013年以降、研修の充実、人材制度・評価制度の見直しを実施。労働時間短縮、両立相談ダイヤルを設置するなどの施策を実施した結果、離職率が3年連続で改善。
ワークライフバランスの取り組み方

では、ワークライフバランスに取り組むためにはどのようなことをしたらいいのでしょうか?
ワークライフバランスの仕組みだけを取り入れたとしてもなかなかそれだけでは実現ができません。
まずそのために、第1番目に経営者側の意識改革が必要です。
そして、その2番目にに管理職に理解してもらい、実践への落とし込みをしっかりしていくことです。
具体的に、「可視化」していくことです。
まず、力の入れどころは「働き方の改革」と「ワークライフバランスを浸透させるための職場風土づくり」です。
「人=投資すべきもの」、「時間は有限」という考え方を管理職、リーダーを中心に繰り返し、理解してもらうために重点的に教育をしていくことが大切です。
リーダー自らが不必要に残業をしない、休日出勤をしない、有休を積極的に取るなどして、リーダーが実践して職場の風土を変えていくことです。
具体的なワークライフバランスの取り組み事例
①育児休暇
必要な女性社員のためだけでなく、「男性社員が育児休暇を活用しやすくすること」がポイントです。
育メンという言葉にも代表されるように、男性社員による育児休暇制度の取得促進が女性の活躍の場を作り、ワークライフバランスを意識改革につながっていきます。
②短時間勤務制度
育児・介護にたずさわっている社員を対象にして、勤務時間を2~3時間、あるいは30分単位で勤務時間を短縮する事例があります。勤務時間に複数のパターンを設け、バリエーションを持たせることが大切なポイントです。
③フレックスタイム制度
1ヶ月以内の期間で総労働時間を規定し、その枠の中で始業・修行時間を決定できる仕組みです。
この制度の優れている点は、総勤務時間を変えないでもいい点です。
そのため、「給与の調整」「昇格・昇給に伴う問題」が起こりにくく取り組みやすいため、最も取り組んでいる企業が多い制度です。企業は、組織としての生産性を損なわないように「一日のうち、必ず勤務するコアタイム」を指定するなどして設置し、効果を上げています。
導入している企業の中には、コアタイムを設けない、フル・フレックス制度を導入している会社もあります。
④テレワーク(在宅勤務)
育児・介護にたずさわる人材の確保ができます。しかし一方で、「リスク管理」「勤怠管理」や、在宅という環境であるため、「情報漏洩リスクの防止」「勤怠管理を適切に行うための仕組みづくり」が求められています。
⑤長時間労働の削減
残業をする風土が根付いている日本企業の多くがこの課題に取り組む必要があります。
「定型作業の廃止」「残業の事前申請化」「業務フローの見直し」などをして残業をなくすために業務内容を分析したり、残業の必要性があるかどうかをしっかり見直していく必要があります。
⑥福利厚生サービスの充実
福利厚生が整っている企業=「社員を大切にしている企業」としてのイメージをもちます。優秀な社員を集めていくためには福利厚生が充実していることが必須です。
まとめ
いかがでしたか?
ワークライフバランスの取り組みは、根付くまでには時間がかかりますが、得られる成果はとても大きいです。これからの企業をより良きものにしていくために、ワークライフバランスの取り組みは、必要な課題です。