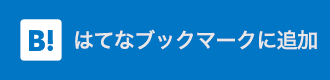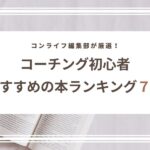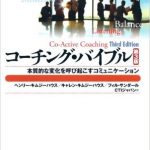目次
はじめに
なにかに夢中になりたくて、
全力で走りたくて、
でも、なにをやっていいか分からなくて……
そんなときは、自分探しの旅に行きたくなりますよね?
だけど、その気持ちを口にすると、
絶対といっていいほど「止めておけ」と笑われてしまいます。
この記事ではそんな「自分探しの旅」を、
ただ感情的に否定することなく、論理的に解説していきます。
自分探しの旅が「無駄だ」といわれる理由

自分探しの旅が否定的に語られる理由は、2つあります。
1つ目は、
自分探しの旅から帰ってきた人には、
「自分が見つかった」という人がまずいないことです。
2つ目は、
「自分探し」という言葉が、
ばく然としすぎていて、
なにを探しに旅をするのか、
旅に出る本人ですらよく分かっていないということです。
そして、
「自分探しの旅」を否定する人々が、
その否定の根拠にしているのが以下の「孔子の論語」です。
子曰く……
「私は十五歳のとき学問に志を立てた。
三十歳になって、その基礎ができて自立できるようになった。
四十歳になると、心に迷うことがなくなった。
五十歳になって、天が自分に与えた使命が自覚できた。
六十歳になると、人の言うことがなんでもすなおに理解できるようになった。
七十歳になると、自分のしたいと思うことをそのままやっても、
人の道を踏みはずすことがなくなった」と。
《出典:論語 旺文社》
孔子ですら天命を知るのに50歳までかかったのだから、
凡人が旅に出たくらいで
「自分(どんな天命をさずかっている人間なのか)」
なんか見つかるわけがない……というわけです。
しかし、
よく考えてみるとこの論法はおかしいですよね?
孔子は優れた人物ですが、
紀元前552年の生まれです。
自動車も飛行機もない時代の人ですし、
もちろんネットもスマホもありません。
50歳までに出会える人の数も旅行できる距離も、
現代人からしてみればたいしたことありません。
そういった環境のなかで
儒教の真髄「論語」を作りあげたから賢者なわけで、
もし現代に生まれていたら、
10歳くらいで天命を自覚しているかもしれません。
それにそもそも孔子は、
21世紀型の旅行を経験していませんから、
「旅に出たけど50歳まで自覚できなかった」
という話ではありません。
もし孔子が21世紀型の旅行をしたら、
旅行をするたびに『論語』レベルの思想を発明したかもしれません。
あれ?
なんだか「無駄だ」といわれる根拠がゆらいできましたよ?
自分探しの旅は、自分を「リセットする」旅

自分探しの旅を否定する決定的な理由はありません。
しかし自分探しの旅をしても、
自分はまず見つからないと思います。
いきなり結論めいたことをいうと、
自分探しの旅には、
自分をリセットする効果があるだけです。
そしてそれは、
人によっては、自分探しをする前に必要なことです。
つまり
旅行が無駄な人もいるし、
旅行をしたほうがいい人もいるんです。
旅行をしたほうがいい理由は以下の通りです。
脳の疲れがとれる
現代人は、
情報過多だと言われています。
常にスマホから情報を得ていて、
脳が
その大量の情報を上手く処理しきれず
疲れているそうです。
脳が極限まで疲れていれば、
思考力も判断力も低下します。
ちなみに、
ブラック企業に勤めている人たちが
辞められずにいるのは、
脳が極限まで疲労していて、
思考力が低下しているからだそうです。
こういった
脳が疲れきった人たちは、
いくら自分を探しても見つかりません。
まずは旅に出て、脳の疲れをとる必要があるのです。
というわけで、
旅をするならスマホの電波が届かないような、
日常を忘れられるような、
そんな土地がいいでしょう。
自分をリセットできる
日常からかけ離れた
環境に身を置くことによって、
脳の疲れがとれてきます。
脳を再起動させたような状態です。
すると心に余裕ができてきます。
今まで(疲れていたので)思いつかなかったようなことが、
どんどん頭に思い浮かんできます。
人によっては、
そのことでたまたま自分が見つかっちゃうかもしれませんが、
実際には、
低下していた知能が旅をすることによって、もとに戻っただけです。
見つかっちゃうような人なら、
疲労さえしていなければ、
旅に出なくても見つけていたはずです。
たいていは、
旅から帰ってしばらくののちに、
探していた自分が見つかります。
これが、
「人によっては、自分探しをする前に旅が必要だ」
といわれる理由です。
数年後への投資となる
「自分」は、現在や未来を探してもありません。
「自分を作る」というのなら話は別ですが、
しかし、
「自分を探す」なら
過去を振り返って
「わたしはこんな人間なんだ」
と認識するものです。
自分探しの旅をしても、
自分はまず見つかりません。
ただし、
数年後に旅を振り返ってみると、
自分が見つかるかもしれません。
たとえば、自分探しの旅をして、
結局自分は見つからなかったけれど、
それをバカ話として飲み会のたびに話していたら、
たまたまその時期に
その国にいたという人がいて、
すっかり盛り上がって友人となり、
その人の紹介で転職をしたら
その会社で画期的な発明をしてしまった
……なんて話は、ちょっと出来すぎですけれど、
それでも
「自分はこの発明をするために生まれてきたのか」
なんて気持ちになりますよね。
自分探しの旅が、
後に「自分」を知るキッカケとなるかもしれません。
自分探しは旅に出なくてもできる

旅に出て自分が見つかる人は、
もう完全に疲れ切っていて、
旅という名のリフレッシュ休暇が必要な人たちです。
普通の人は、
旅に出なくても自分を探せますし、
旅に出ても自分は見つかりません。
なぜなら、答えは自分のなかにあるからです。
以下は、
自分を見つけるキッカケとなったもののほんの一例です。
旅日記を創作してみる
旅に出たつもりで、
旅日記を書いてみてください。
こんな国を旅行したいなあという願望でもいいですし、
漫画の世界や宇宙など、
まったくの創作でもかまいません。
クリエイティブ系の専門学校では、
こういった課題をよくするのですが、
生徒によって
「書いていて楽しいもの」はまったく違います。
ハワイやローマのような
実在する都市の旅行を想像するのが楽しい人がいます。
その一方で、
架空の惑星への旅行を創作することが楽しいという人もいます。
主人公になりきって旅行を楽しんでいる人もいますし、
どんな日記を書いたら読んだ人に喜ばれるか、
そんなことを想像しながら書くのが楽しいという人もいます。
主人公を自分そっくりにして
没入するのが楽しいという人や、
逆に自分とは正反対の性格や性別で
書くのが楽しいという人もいます。
たくさん書いているうちに、
自分がどんなことをしているときに
楽しいと感じるのかが分かってきます。
ありのままの自分が見えてきます。
目の前のことを全力でやってみる
いつまでも考えていないで、
とりあえず行動してみる……
このような考えかたは、実は正しかったりします。
というのも、
人間には「作業興奮」という仕組みがあるからです。
これは簡単に説明すると
「なにか作業をすると、
そのことによって脳が刺激をされて、
やる気がわいてくる」
という仕組みです。
つまり、
なにをやっていいのか分からないなら、
とりあえずなにかやってみると、
そのことによって欲望がわいてくる……
なにをやりたいのかが見えてきます。
それに全力でなにかをやってみると、
意外なところから天職が見つかるかもしれません。
脳が疲れすぎないよう気をつけて、
全力でなにかやってみましょう。
好きなことを徹底的にやる
好きなことを徹底的にやってみるのも1つの方法です。
これは実際にやってみたことなんですが、
海外ドラマを4ヶ月で70本観たことがあります。
仕事なので、
つまらないと思っても10話目までは観ました。
面白いものは50話以上観ています。
これくらいの量を視聴していると、
だいたいドラマのパターンが分かってきます。
世間の評価とは関係なく、
好きな作品、苦手な作品というのが出てきます。
好きな展開、好きな人物、嫌悪する対象などなど、
自分の作品の見かたが分かってきます。
好きなことを徹底的にやることは、
自分の内面を見つめることにもなるんです。
まとめ
自分探しで旅に出ても自分はまず見つかりません。
なぜなら答えは自分のなかにあるからです。
まずは深く思考し、
ありのままの自分を直視し、
自分とはなにかを知ることです。
自分を正確に知ることができれば、
存分に能力が発揮できます。
また、自分に合った仕事を選ぶこともできるでしょう。